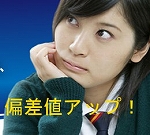博士研究員(ポストドクトラルフェロー)の給料
- 2013年04月01日
- カテゴリ:未分類
東大、京大等の旧帝国大学や、その他の国公立大学、私立大学を出て大学院に入り、博士号を取得すると、就職先の問題が出てきます。
会社に就職する人は別として、アカデミック・ポスト(通称アカポス)につきたい人は、博士修了までに就職先が決まってなければポスト・ドクトラル・フェロー、通称ポスドクになるのが一般的です。
これは日本だけでなく、アメリカ等世界中で同じと思われます。
博士号を取った後、海外の研究室で武者修行をし、素晴らしい実績を上げれば、日本の大学に准教授や教授で帰ってくる人がいますが、これは非常にいいパターンです。
海外でポストドクをやって、なかなか帰るポストが見つからず、ずっとアメリカの研究所でポストドクを続ける人や、研究を諦めて別の道に進む人もいます。
日本ではもっと事情は苦しく、ポストドクになってもその後の永久職つまり、一生勤められる勤務先が見つからない人が多くいます。そういう場合はポストドクを転々とするのですが、ポストドクは採用時に35歳までと決まっているものも多く、40歳近くになるとポストドクの口が無くなって大学の職員(技官)になる人もいたりします。
あるいは、先生の力があれば、プロジェクト研究費を取ってきて、40歳以上でもポストドクを続けられる人もいます。そして超ラッキーな人は、40半ば位で永久職のポジションを得られる場合もありますが、それは極めて例外的な成功例とも言えるでしょう。
ポストドクの給料ですが、昔は非常に潤沢で、NEDOでは、年間960万、750万、600万、400万位のランクがあり、スーパーポストドクは年収1000万円近くもらってました。
しかし、最近聞いた話では、ポストドクの給与は年収300万位、という話もあるようです。大学や研究室にもよるので一概には言えませんが、すごい落差です。これは就職先の無いポストドクが増えたのでより多くの人に予算を割り振るようになったので1人あたりの給与が減った面もあるようです。
そのため元々高学歴ワーキングプアの代表のように言われていた博士研究員がますますプアになってきている面があるようです。
そういうことを考えると、研究者を夢見て博士号を取り、将来ノーベル賞級の仕事をしようと頑張っている博士研究員の将来は必ずしもバラ色ではありません。
アメリカでは教授がベンチャー企業を持っていてそこで博士研究員を雇うケースもあるようですが、日本には儲かっているベンチャー企業はほとんどないのでそれも難しいです。
日本からもグーグルやフェイスブックのようなベンチャー企業が出てくればポストドクの問題は解消するのでしょうけど。